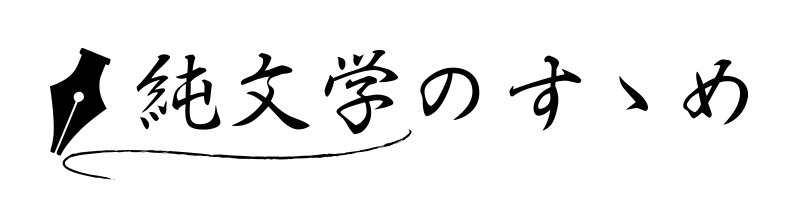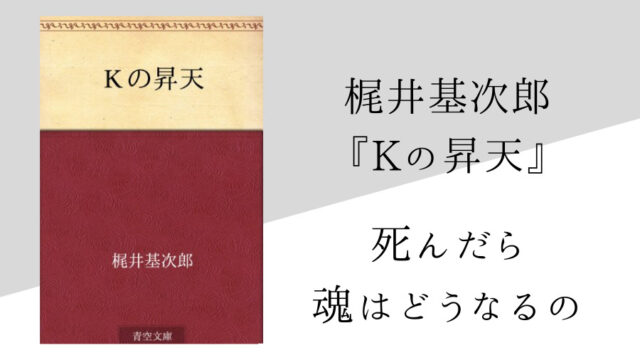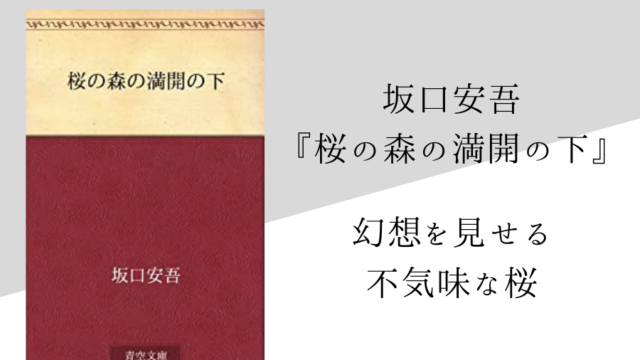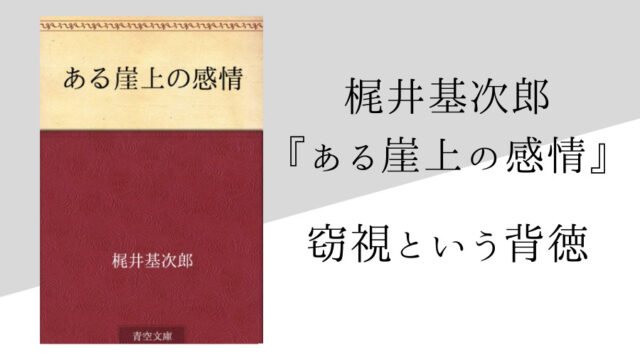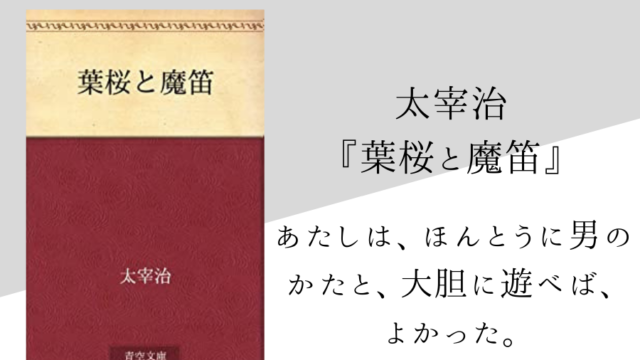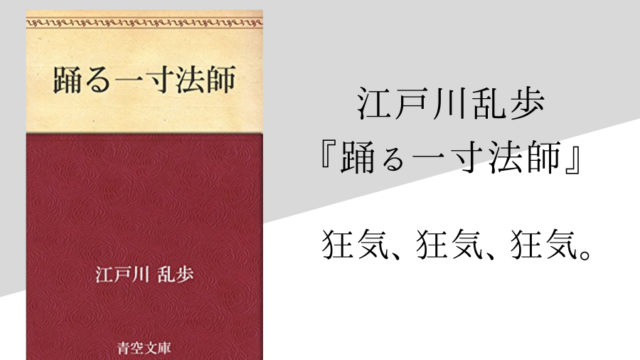今回は、小川洋子『先回りローバ』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!
Contents
『先回りローバ』の作品概要
| 著者 | 小川洋子(おがわ ようこ) |
|---|---|
| 発表年 | – |
| 発表形態 | 雑誌掲載 |
| ジャンル | 短編小説 |
| テーマ | イマジナリーフレンド |
『先回りローバ』は、2018年1月に幻冬舎から刊行された短編集『口笛の上手白雪姫』に収録された小川洋子の短編小説です。吃音の7歳の少年が、不思議なローバと出会った記憶がつづられています。
著者:小川洋子について
- 1962年岡山県生まれ
- 早稲田大学文学部文芸科卒業
- 『揚羽蝶が壊れる時』でデビュー
- 『妊娠カレンダー』で芥川賞受賞
小川洋子は、1962年に生まれた岡山県出身の小説家です。早稲田大学文学部文芸科卒業後、1988年に『揚羽蝶(あげはちょう)が壊れる時』で海燕(かいえん)新人文学賞を受賞しました。
1991年には『妊娠カレンダー』で第104回芥川賞を受賞し、一躍有名作家となりました。同時代作家の吉本ばななと並んで評価されることが多い作家です。
『先回りローバ』のあらすじ
吃音持ちの主人公は、自分の名前を名乗ることを最も苦手としていました。そしてこの吃音の原因は、両親が主人公の誕生日を実際より6日後に届けたからだと主人公は信じています。
その日は〈集会〉の主宰者の誕生日か何かで、両親は何としてもその日を息子の誕生日にしたかったのです。
そんなとき、主人公はふと小さなお婆さんの存在に気づきます。主人公は、彼女といるときだけ不思議と一度もつっかえずに話すことができました。僕は彼女とのおしゃべりを楽しみますが、いずれ別れがやって来るのでした。
登場人物紹介
僕
吃音の少年。両親が〈集会〉に行っている間に電話番をしているが、時報を聞いて電話が鳴らないようにしている。ある日、小さなローバの存在に気づく。
ローバ
「僕」が7歳のときに現れた小さな女。「僕」の言葉を箒と塵取りで集める。
両親
「僕」の親。定期的に〈集会〉に出かけ、留守の間 息子に電話番をさせている。
『先回りローバ』の内容
この先、小川洋子『先回りローバ』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。
一言で言うと
吃音の克服
僕と電話
僕が7歳のとき、家に初めて電話が引かれました。定期的に〈集会〉に出かける両親は僕に電話番をさせ、「電話が鳴ったら、まず自分の名前を名乗る」と言い聞かせますが、吃音の僕は自分の名前を発音することが一番苦手でした。
この吃音の原因は、両親が僕の誕生日を実際より6日後に届けたからだと僕は信じています。その日は〈集会〉の主宰者の誕生日か〈集会〉の設立記念日かで、両親は何としてもその日を息子の誕生日にしたかったのです。
そのせいで僕の前には〈六日分の空白〉が存在し、僕の言葉はその空白に吸い込まれてしまうのでした。
そういうわけで電話があっても話せない僕は、両親が出かけている間時報を聞くようになります。時報を聞いていれば電話がかかってくることはなく、両親には「電話はなかった」と報告できるからです。
時報のお姉さんはくたびれることなく、途切れずにひたすら時刻を知らせ続けます。お姉さんは答えを求めず、名乗らなくても変に思ったりしないため、僕は安心して時報を聞いていられるのでした。
ローバとの出会い
そんなとき、僕はふとお婆さんの存在に気づきます。彼女は人差し指と親指を開いて表せるくらいの小さなお婆さんで、彼女と話す時、僕の言葉は一度もつっかえないのでした。
箒と塵取りを持って腰をかがめている彼女に「絵本に出てくる老婆みたい」と言うと、彼女は唇をとがらせて「できましたらせめて、カタカナにして下さいませんでしょうか」と言いました。
そして、ローバは先回りしてしまっている僕の声を回収しているのだと言います。ローバは塵取りの中身を前掛けのポケットに手慣れた様子で入れました。
先回りローバが現れるタイミングを予測することは困難でしたが、現れた時にはとりとめのないおしゃべりをしました。
本当の誕生日
誕生日、それは僕にとって一年中で最も憂鬱な日です。〈集会〉に連れて行かれ、〈六日分の空白〉を改めて押し付けられる日だからです。
その後ついに、時報のお姉さんとの突然の別れが訪れました。両親はひどく気分を害し、電話代の請求書を突きつけます。〈六日分の空白〉がいつにも増してひんやりとしていたため、「ごめんなさい」と言うまでにいっそう時間がかかりました。
僕は時報のお姉さんともう会えなくなったことをローバに話し、「元気の出ない理由が、もう一つあるよ」「もうすぐ誕生日なんだ」とローバに告げます。僕の誕生日が実際とは異なることを知ったローバは、「本当の誕生日をお祝いすればよろしいのですよ」と言いました。
嘘の誕生日の6日前、ローバが歌ったハッピーバースデー・トゥー・ユーを僕は今でも覚えています。その8歳の本当の誕生日が、先回りローバの姿を目にした最後の日となりました。そして気がつくと僕の吃音は治っていました。
『先回りローバ』の解説
現代的ファンタジー
本作は、声を回収する小さなローバが現れるファンタジー要素のある物語です。完全なお伽噺ではなく、日常の中にそのエッセンスを自然に挿入する必要がありますが、その一手を担っているのが「登場人物の不明瞭な素性」です。
小さなローバの正体が明かされないのは自明のこととして、主人公の「僕」については、7歳の吃音の持ちの少年であるということ以外、容姿や他者とのかかわりなどパーソナルな情報がありません。
幼稚園時代の出来事は、エピソードとして組み込まれているだけで「僕」の輪郭が読み取れるような内容ではありませんでした。
さらに「僕」の両親についての情報も、「定期的に〈集会〉に参加している」という事実だけで勤め先も交友関係も容貌も分かりません。
また、両親は吃音の子供に電話番をさせるという酷な一面がありますが、「両親は息子に何が起こっているのか、ほとんど気づいていなかった」という語りがあります。
吃音が発話障害として認識されていなかった時代なのかもしれませんが、7歳になるまで息子の異変に気づけないのは少々不自然です。
両親は楽観的であるため吃音に気づいていないと語られていますが、単純に息子に興味がないのではないかと思われる描写があります。下記は、「僕」が時報を聞いていたことを知ったときの場面です。
彼らは自分たちの知らないところで息子がこっそり何かをやっていたことに、腹を立てているのではなかった。ただ無駄なお金を支払わなければならないのが、忌々しいだけだった。
一般的に、息子がこっそり何かをしていたら「なぜ時報を聞いていたのか」「なぜ隠れて聞いていたのか」その行動の理由にフォーカスしそうですが、両親は電話料金を払わなければいけない事実に腹を立てているだけです。
また、両親は〈集会〉にまつわる日付を自分の息子の誕生日にしてしまうほど〈集会〉に熱中している人物です。ここから、〈集会〉が最優先で息子は二の次という両親像が浮かんできます。
こうした無機質な人間味のなさも、現実味を薄めてより架空の物語であることを強調し、小さなローバという実際には現れない存在を違和感なく挿入する装置になっていると言えます。
そして、物語の最後には「これは、油断すると自分でも忘れてしまうくらい遠い昔の話なので、ここに記しておこうと決めた」とあり、かなり未来からの過去回想であることが分かります。
さらに、冒頭の「初めて家に電話が引かれたのは、僕が七つの時だった」という語りから、現在からは遠い昔の話であることが分かります。これらも、現実味を帯びさせずに物語感を増させる仕組みかと考えます。
『先回りローバ』の感想
不穏な空気
『先回りローバ』は、終始モノクロな物語だったと読み終えて思いました。普段、小説は情景をイメージしながら読むのですが、その情景が白・黒・グレーで構成されていました。
そのため、『妊娠カレンダー』や『ドミトリィ』など他の小川作品を読んだときに感じたような、何かよくないことが起きそうな胸騒ぎを感じました。
「僕」の吃音は最終的に治り、明るい方に向かうところで物語は終わりますが、それまでは不穏な空気で充ちている作品だと思います。
このモノクロの要因は、【解説】で触れた通り語り手が必要最低限の情報しか読者に提供しないからです。「僕」や両親に関する情報はありませんが、物語の核となるローバや電話、時報に関する語りは散見されます。
特に印象的だったのは「僕」が初めて電話を見た時の描写です。黒電話を実際に使ったことはありませんが、確かに日常的に使うものであるにもかかわらずあまり実用的ではない見た目というか絶妙に魅力的なフォルムだと思います。
形容詞がたい丸み、暗号めいたダイヤル、耳にフィットするよう計算された受話器のカーブ、可愛らしげにクルクルとカールするコード。そうした何もかもがどこかしたおもちゃめいていたが、僕は最初からそれが、ただものではないことにちゃんと気づいていた。
登場人物の心の支えとして、人間ではなく機械的に単調に時を告げる時報がピックアップされるのが、意外であり興味深いと思いました。
最後に
今回は、小川洋子『先回りローバ』のあらすじと内容解説・感想をご紹介しました。
ぜひ読んでみて下さい!