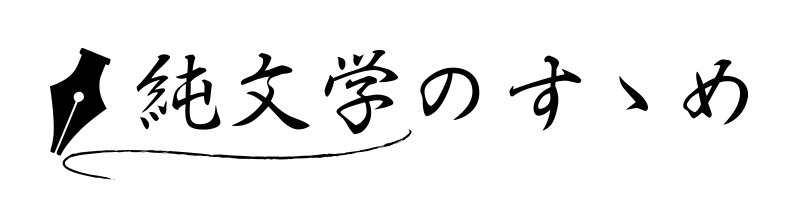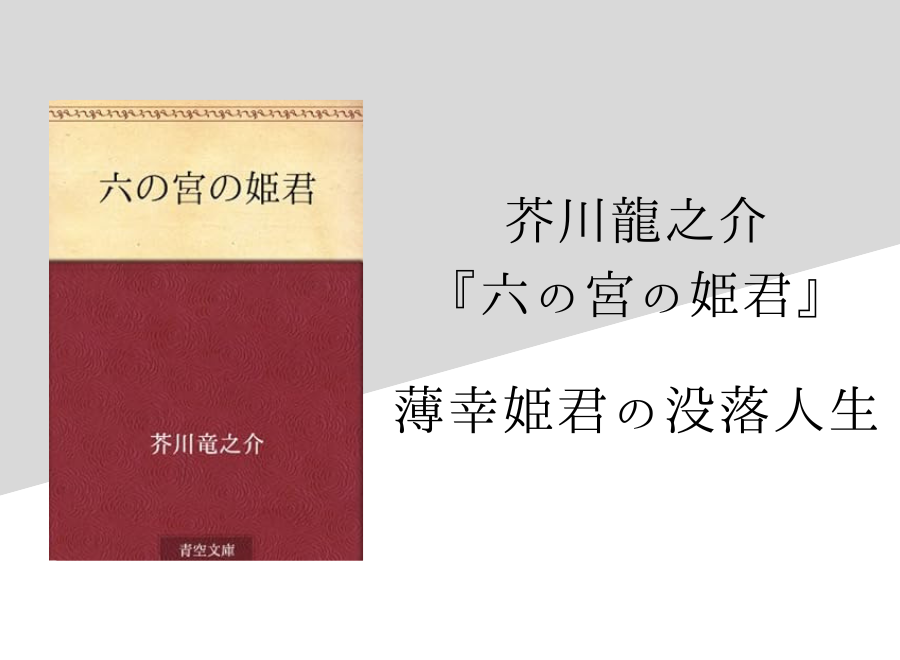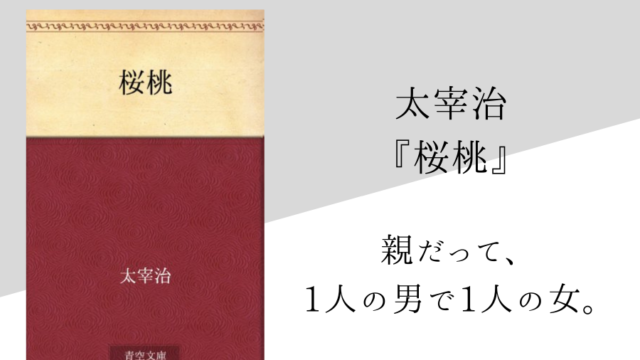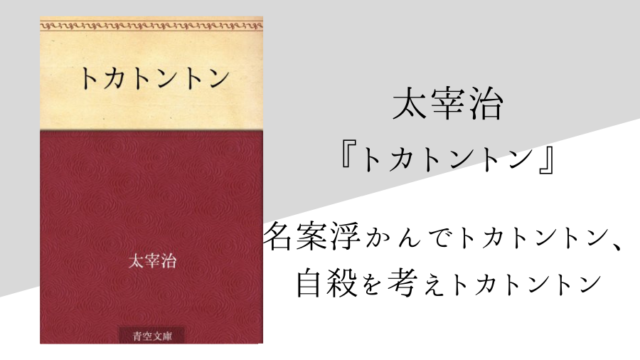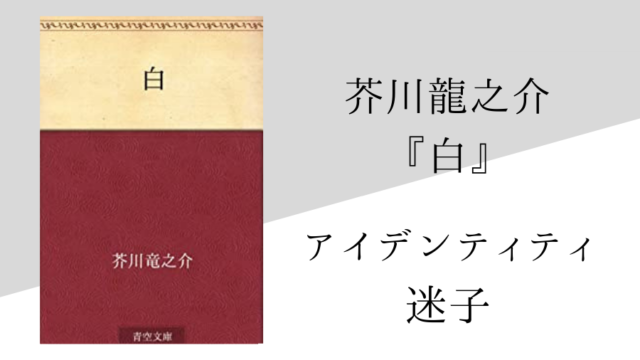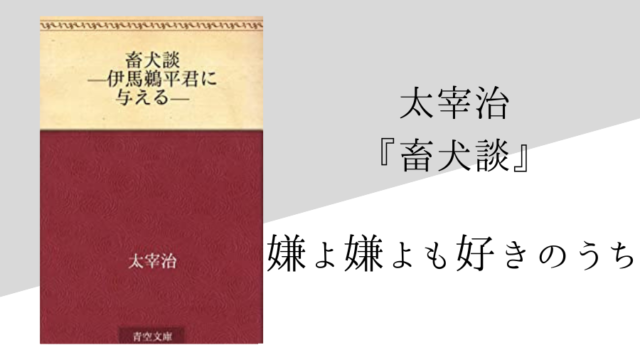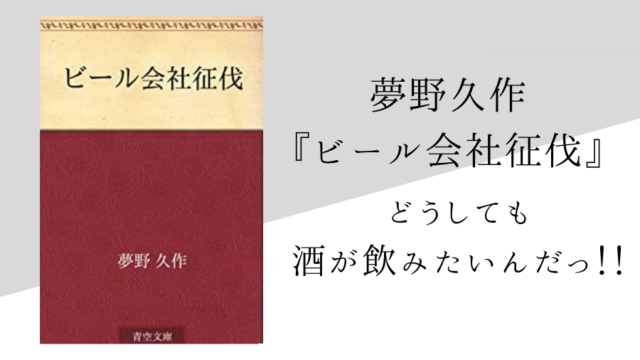今昔物語を典拠とし、芥川の歴史小説の傑作と評される『六の宮の姫君』。
今回は、芥川龍之介『六の宮の姫君』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!
Contents
『六の宮の姫君』の作品概要
| 著者 | 芥川龍之介(あくたがわ りゅうのすけ) |
|---|---|
| 発表年 | 大正11年 |
| 発表形態 | 雑誌掲載 |
| ジャンル | 短編小説 |
| テーマ | 虚無的な人生観 |
『六の宮の姫君』は、1922年に雑誌『表現』(8月号)で発表された芥川龍之介の短編小説です。
Kindle版は無料¥0で読むことができます。
著者:芥川龍之介について
- 夏目漱石に『鼻』を評価され、学生にして文壇デビュー
- 堀辰雄と出会い、弟子として可愛がった
- 35歳で自殺
- 菊池寛は、芥川の死後「芥川賞」を設立
芥川龍之介は、東大在学中に夏目漱石に『鼻』を絶賛され、華々しくデビューしました。芥川は作家の室生犀星(むろう さいせい)から堀辰雄を紹介され、堀の面倒を見ます。堀は、芥川を実父のように慕いました。
しかし晩年は精神を病み、睡眠薬等の薬物を乱用して35歳で自殺してしまいます。
芥川とは学生時代からの友人で、文藝春秋社を設立した菊池寛は、芥川の死後「芥川龍之介賞」を設立しました。芥川の死は、上からの啓蒙をコンセプトとする近代文学の終焉(しゅうえん)と語られることが多いです。

『六の宮の姫君』のあらすじ
登場人物紹介
姫君
高貴な家の生まれ。大人寂びた美しさをそなえている。
男
丹波の前司。優しい心の持ち主で顔かたちも雅で美しい。
乳母
献身的に六の宮の姫の世話している。両親を失った姫君を心配し、縁談を持ちかける。
『六の宮の姫君』の内容
この先、芥川龍之介『六の宮の姫君』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。
一言で言うと
薄幸姫君の没落人生
六の宮の姫君
昔気質で時勢に遅れがちではあるものの、高貴な父母のもとに生まれた姫君は、両親に寵愛(ちょうあい)されて育ちました。
しかし、両親は姫君を進んで誰かにめあわせることはなく、言い寄る誰かをひたすら待つのみでした。世間知らずの姫君は、格別不満を感じることなく日々を過ごします。
そんなとき突然父親が亡くなり、半年以内に母親も跡を追うように故人となってしまいました。頼りにするものを失った姫君は、乳母と2人でつらい暮らしを余儀なくされます。
あるとき、乳母は姫君に丹波の前司なにがしの殿が姫君に会いたがっていることを伝えました。そして乳母の助言により、苦しい生活から抜け出すために姫君はその男と会うようになります。
当初姫君は生活のために体を売るのも同然と悲しみましたが、男との逢瀬を重ねるにつれて、悲しみも少ないと同時に喜びも少ない日々の中に、はかない満足を見出すようになっていきました。
別離
ところがある夜、男は唐突に京を離れなければならないことを姫君に告げました。父親が陸奥守(むつのかみ)に任命されたため、男も伴って陸奥に下ることになったのです。そして任務が終わる5年後の再会を約束して、男は陸奥へ旅立つのでした。
やがて旅立ちから6年目の春がやって来ましたが、男はついに都へは帰りませんでした。姫君の家の召使は一人残らず立ち退き、家は荒れ放題です。乳母はまた他の男との縁談を持ちかけますが、姫君はそれを受け入れませんでした。
その頃、男は遠い常陸(ひたち)の国の屋形で、父の意に沿った新しい妻と酒を酌んでいました。しかし、男は姫君のことを忘れかねていました。
悲しい再会
男が京を発ってから9年目の晩秋に、男は常陸の妻とその親族と上京しました。男は妻を妻の父の屋形に送り届け、荷物も解かずに六の宮へ向かいます。
姫君の住まいはかつての姿を残しておらず、廃墟と化していて姫君の姿はありません。男はその廃墟のなかに見つけた老尼から別れた後の姫君の辛い暮らしぶりを聞きました。
男は翌日から姫君を探して洛中を歩き回り、数日後に雨宿りのために立ち寄った朱雀門の西の曲殿の軒下で、痩せ枯れた姫君とそれを介抱する乳母を見つけます。
男が姫君の名前を呼ぶと、姫君は男を見てかすかに叫び、筵(むしろ)の上にうつ伏してしまいました。
乳母は、慌てて同じく軒下で雨宿りをしていた乞食法師に読経を頼みます。法師は姫君に自身で念仏を唱えて往生するよう言うと、姫君は細々と仏名(ぶつみょう)を唱え出しましたが、突然天井に火の車や金色の蓮華が見えると呟きました。
法師はほとんど叱るように念仏を勧めますが、姫君は「何も、――何も見えませぬ。暗い中に風ばかり、――冷たい風ばかり吹いて参りまする。」と言い、その顔はだんだん死に顔に変わっていくのでした。
不憫な魂
姫君の死から何日後、姫君に念仏を勧めた法師は朱雀門の前の曲殿で膝を抱えていました。そこに通りかかった侍が「この頃この朱雀門のほとりに、女の泣き声がするそうではないか?」と声をかけます。
法師が侍に「お聞きなされ」と言うと、突然どこからか女の声が細々と嘆きを送り、どこかへ消えていきました。
「あれは極楽も地獄も知らぬ、不甲斐ない女の魂でござる。御仏を念じておやりなされ」と語る法師の顔を侍がのぞきこむと、いきなりその目の前に両手をつきます。
この乞食法師は、世にも名高い内記の上人(しょうにん)であり、やんごとない高徳の沙門(しゃもん)だったのです。
『六の宮の姫君』の解説
現代に通じる感覚
海老井氏(参考)は、『六の宮の姫君』と原話『今昔物語(六の宮の姫君の夫出家せる語第五)』との違いを明確にし、複数ある相違点のうち特にクライマックスシーンに着目しています。(傍線・筆者)
①零落しきった姫君とその夫との再会、それに続く姫君の死を描いたこの作品のクライマックスの場面で、原話に比べて姫君の臨終の描写が著しく精しくなり、さらに、原話では姫君は夫を認めた瞬間に死ぬのに対して、芥川の作品では、姫君は中有に迷う姿に描かれている。
②原話は姫君の夫が出家することをもって結びとしているが、芥川は姫君の死後の夫については何も述べず、原話にない後日諌を付け加えている。姫君が「極樂も地獄も知らぬ、騎甲斐ない女」の魂として迷っていることを迷べ、姫君の臨終に立会った乞食法師(原話にはない)が、実は「やん事ない高徳の沙門」「内記の上人」だったという種明かしを結びとしている。
この相違は、姫君の心情に対する芥川の心理的共鳴が関係していると指摘されました。
芥川は日本の歴史小説について「古人と今人に共通する心理からひらめきを得たものが多い」と述べています。
海老井氏は『六の宮の姫君』もそれに該当すると考え、芥川が「古人(姫君)と今人(芥川)に共通する心理」として「虚無的な人生観」を見出したとしています。
物語の結びの部分では、芥川の代弁者として原話に描かれない法師が登場し、「極樂も地獄も知らぬ、腑甲斐ない女」と語りました。これが芥川自身の姫君の解釈であり、芥川はこの姿に共感をしました。
その背景として、海老井氏は芥川の人生観の変化に着目しています。死は瞬間的、燃焼的なものであるという理解から、中有的(人が死んでから次の生を受けるまでの期間)なもの、時間的に幅があるものという風に変化しており、これは姫君の死とリンクします。
こうして芥川は、原話に死んでも死にきれない姫君の姿を見て、姫君の臨終の場面を「極樂も地獄も知らぬ、腑甲斐ない女」の死として、成仏できずにただようように描いたとしています。
海老井 英次「『六の宮の姫君』の自立性」(「語文研究 24」1967年10月九州大学国語国文学会)
『六の宮の姫君』の感想
虚ろな姫君
『六の宮の姫君』に登場する姫君は、宮中の女性らしく受け身な人物として描かれていますが、「悲しみも知らないと同時に、喜びも知らない生涯」という語られているように、もはや受け身というより何事にも興味を示さない虚ろな印象を受けました。
両親が亡くなっても「悲しいというより途方に暮れずにはいられ」ず、乳母に紹介された男とむつび合うときも「嬉しいとは一夜も思わなかった」としています。
そしてしまいには「わたしはもう何も入らぬ。生きようとも死のうとも一つ事じゃ」と語っています。
芥川は、こうした姫君の消極的な姿に「虚無的な人生観」(解説)を見たのだと思いました。
また、芥川を慕った作家・堀辰雄の『曠野』は『六の宮の姫君』と関連があります。
堀辰雄『曠野』は『今昔物語』巻三十「中務の大輔の娘、近江の郡司の婢と成れる語第四」を典拠としていますが、同時に『六の宮の姫君』の典拠である『今昔物語』巻十五「六の宮の姫君の夫出家せる語第五」も参考にしています。

最後に
今回は、芥川龍之介『六の宮の姫君』のあらすじと内容解説・感想をご紹介しました。
ぜひ読んでみて下さい!
↑Kindle版は無料¥0で読むことができます。