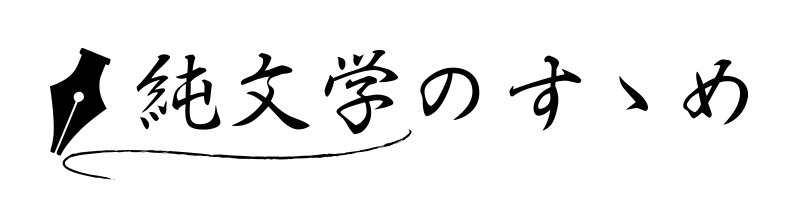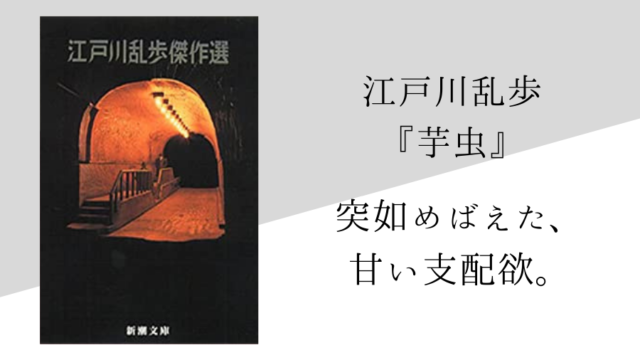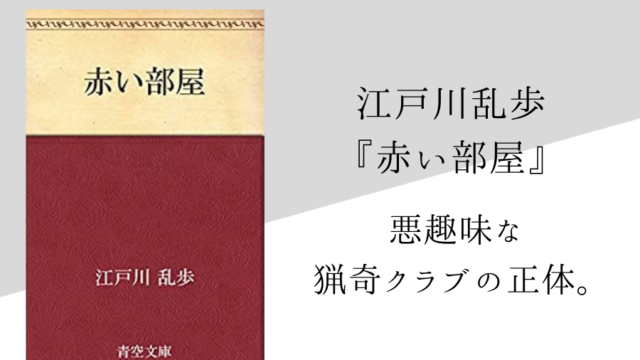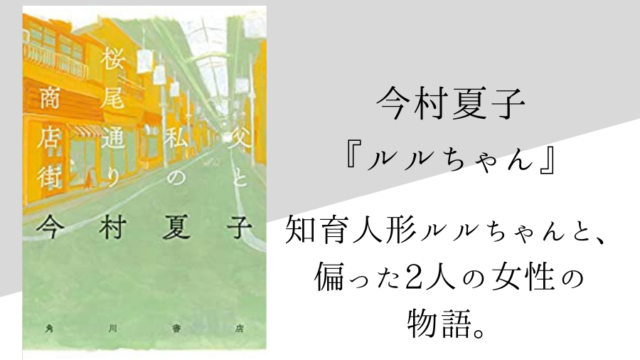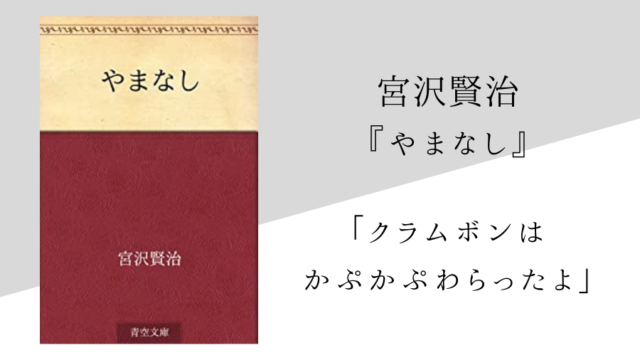『大川(おおかわ)の水』は、下町出身の「自分」が隅田川の魅力を語る作品で、芥川が初めて発表した散文とされています。
今回は、芥川龍之介『大川の水』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!
Contents
『大川の水』の作品概要
| 著者 | 芥川龍之介(あくたがわ りゅうのすけ) |
|---|---|
| 発表年 | 1914年 |
| 発表形態 | 雑誌掲載 |
| ジャンル | 短編小説 |
| テーマ | 慰安と寂寥(せきりょう) |
『大川の水』は、1914年4月に雑誌『心の花』で発表された芥川龍之介の短編小説です。隅田川をキーワードに東京が語られています。
『大川の水』は、それまで詩歌(韻文)に注力していた芥川の、記念すべき散文デビュー作です。Kindle版は無料¥0で読むことができます。
著者:芥川龍之介について
- 夏目漱石に『鼻』を評価され、学生にして文壇デビュー
- 堀辰雄と出会い、弟子として可愛がった
- 35歳で自殺
- 菊池寛は、芥川の死後「芥川賞」を設立
芥川龍之介は、東大在学中に夏目漱石に『鼻』を絶賛され、華々しくデビューしました。芥川は作家の室生犀星(むろう さいせい)から堀辰雄を紹介され、堀の面倒を見ます。堀は、芥川を実父のように慕いました。
しかし晩年は精神を病み、睡眠薬等の薬物を乱用して35歳で自殺してしまいます。
芥川とは学生時代からの友人で、文藝春秋社を設立した菊池寛は、芥川の死後「芥川龍之介賞」を設立しました。芥川の死は、上からの啓蒙をコンセプトとする近代文学の終焉(しゅうえん)と語られることが多いです。

『大川の水』のあらすじ
語り手の「自分」が大川について語ります。自分は、大川にたいして慰安と寂寥・なつかしさとさびしさという矛盾する印象を持っています。同時に、自分は大川の水の響きとの水の光のために、東京を愛するのだと語りました。
登場人物紹介
自分
大川に近い町出身。大川から感じるイメージや印象をつぶさに語る。
『大川の水』の内容
この先、芥川龍之介『大川の水』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。
一言で言うと
なぜ大川を愛するのか
慰安と寂寥
大川の近くに生まれた「自分」は、幼い頃から大川に親しんでいます。そして、「なぜ、濁った生暖かい大川をこれほど愛するのか」と自分に問いかけました。
自分は、涙を流したくなるような、なつかしさとさびしさを大川に感じるがゆえに、大川を愛しているのです。
そして大川の魅力は、その水の音と光にあります。さびしげな水の響きは古典芸能の見せ場で効果的に使われ、渡し船の中ではなつかしく感じられます。
なめらかさと暖かさを持っている水の光には人間味があり、特に川の上に立ちこめる水蒸気と夕闇の中の大川の水は、なんともいえない微妙な色を帯びているのでした。
そして自分は、大川の水の音と光を愛するがゆえに、大川が流れる東京とそこでの生活を愛するのでした。
『大川の水』の解説
『大川の水』の表現
『大川の水』の文体の特徴は、さまざまな修辞法が用いられている点です。(参考:①早澤論)
●その水の声のなつかしさ、つぶやくように、すねるように、舌うつように、草の汁をしぼった青い水
●ただ淡水と潮水とが交錯する平原の大河の水は、冷やかな青に、濁った黄の暖かみを交えて、
●皺をよせて、気むずかしいユダヤの老爺のように、ぶつぶつ口小言を言う水の色
特に「冷やかな青」「ぶつぶつ口小言を言う水の色」などは変わった表現です。これには、『大川の水』が発表されたころに「印象主義」が流行していたことが関係しています。印象主義は、五感を使った描写を指します。
その中でも、五感の組み合わせによる表現を「感覚描写」と言います。「冷やかな青」は触覚と視覚の組み合わせで、「ぶつぶつ口小言を言う水の色」は聴覚と視覚の組み合わせです。
感覚に重点を置き、自分が感じたことをそのまま表現する点で、印象主義は主観的な手法です。一方でそれまで主流だった自然主義は、自分を後ろに追いやって、ありのままの現実を主観を交えずにそのまま描くという点で客観的な手法です。
感覚描写は、言い換えれば共感覚による表現です。共感覚とは、ある1つの刺激に対して複数の感覚を覚える現象のことです。共感覚を持つ人は、音に色を感じたり(聴覚+視覚)、味に形を感じたり(味覚+触覚)することがあります。
共感覚を持った作家には、梶井基次郎(かじいもとじろう)が挙げられます。彼の代表作『檸檬』には、「あのびいどろの味ほど幽かな涼しい味があるものか」という一文があります。「涼しい味」は、触感と味覚が組み合わさった表現です。
芥川はこうした手法を用いて、大川を豊かに描写しました。
①早澤 正人「感覚の変容 : 「老狂人」「死相」から「大川の水」へ」(『文学研究論集』(37) 75-87頁 2012年)
②佐藤 嗣男「「大川の水」小論 : 白秋的世界との同質性と異質性(六月第一例会・討議資料)」(『文学と教育』(108) 28-36頁 1979年)
『大川の水』の感想
慰安と寂寥の正体
本文の中で印象的なのは、「その後『一の橋の渡し』の絶えたことをきいた。『御蔵橋の渡し』の廃れるのも間があるまい。」という一文です。この文章はどこの段落にも属さず、追記のような形で最後の文から一行開けてポツンと置かれています。
「渡し」は渡し船のことです。かつて吾妻橋から新大橋までの間にには5つの渡しがありましたが、1つずつ姿を消してついに「一の橋の渡し」と「御蔵橋の渡し」だけになってしまいました。
しかし『大川の水』を書き終えたあと、自分は「一の橋の渡し」もなくなってしまったことを聞きました。「御蔵橋の渡しがなくなってしまうのも時間の問題だろう」と、自分は思ったのです。
私は、ここに消えゆくもののむなしさ・さびしさを感じました。「時代に合わないものがすたれていくのは仕方がない。しかし、分かってはいてもやはりさびしい」というような感覚です。しかし、自分は次のようにも述べています。
自分はひとり、渡し船の舷に肘をついて、もう靄のおりかけた、薄暮の川の水面を、なんということもなく見渡しながら、その暗緑色の水のあなた、暗い家々の空に大きな赤い月の出を見て、思わず涙を流したのを、おそらく終世忘れることはできないであろう。
「渡し船の舷に肘をついて」見た景色に「思わず涙を流したのを、おそらく終世忘れることはできない」と自分は語っています。渡しはなくなっても、自分の記憶には残り続けることが示されているのです。
自分は、記憶の中に大川を生かし続けることができることに気づき、「大川の記憶を自身のものだけでなく、これを読んだ人にも共有したい」という願いを込めて、『大川の水』を書いたのかもしれないと思いました。
最後に
今回は、芥川龍之介『大川の水』のあらすじと内容解説・感想をご紹介しました。
特に下町に住んでいる・下町出身の人は共感できるポイントがたくさんある小説です。ぜひ読んでみて下さい!
↑Kindle版は無料¥0で読むことができます。