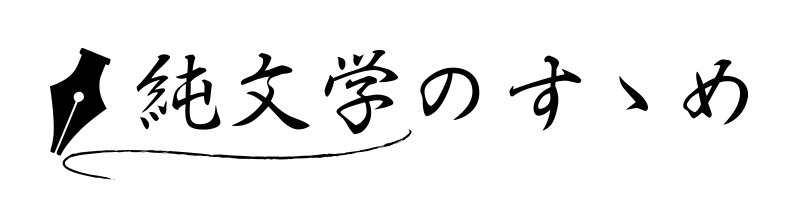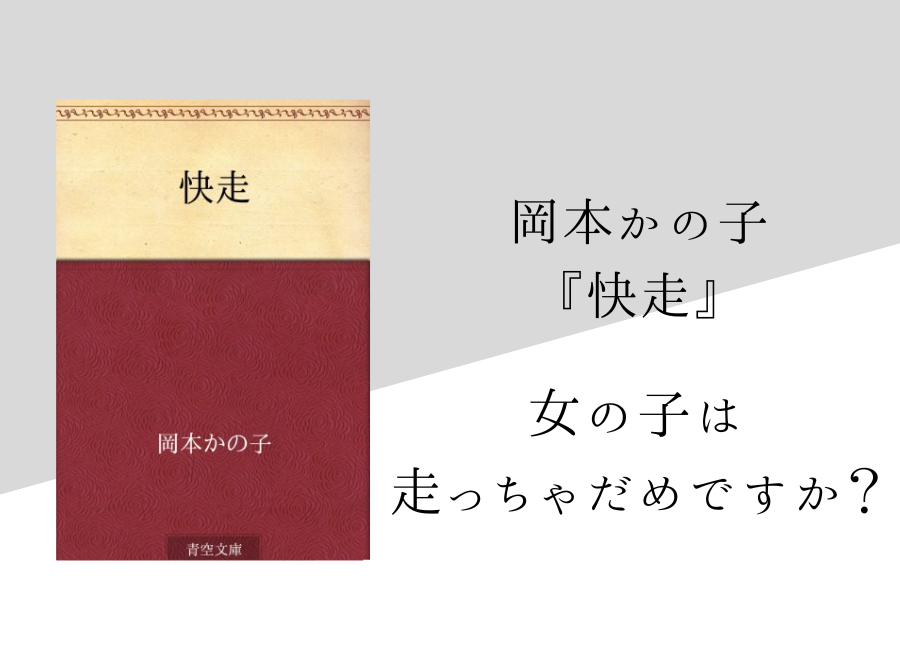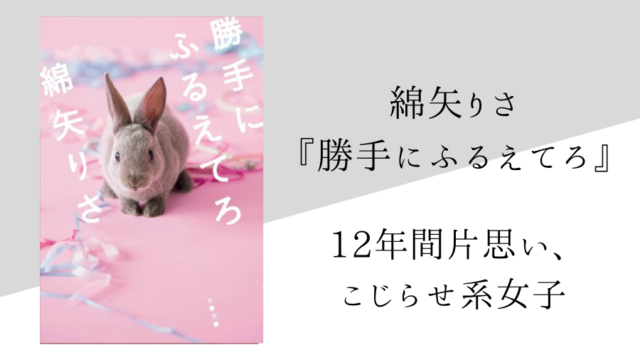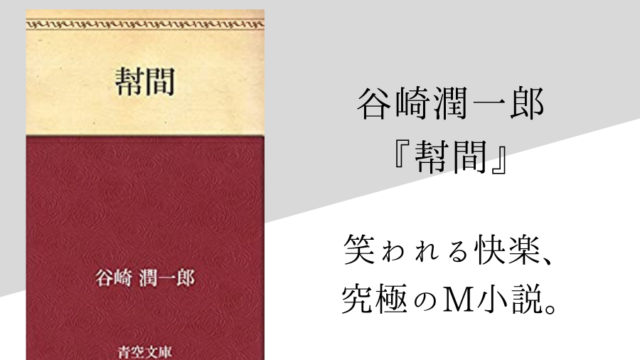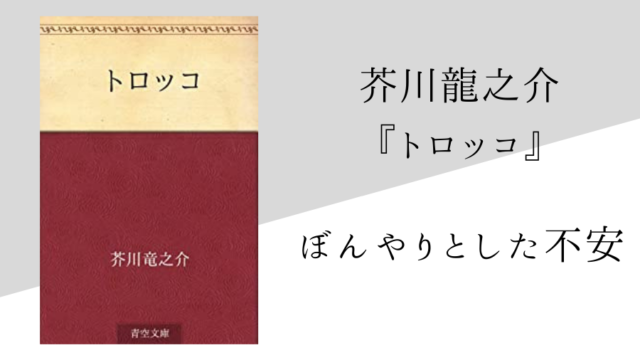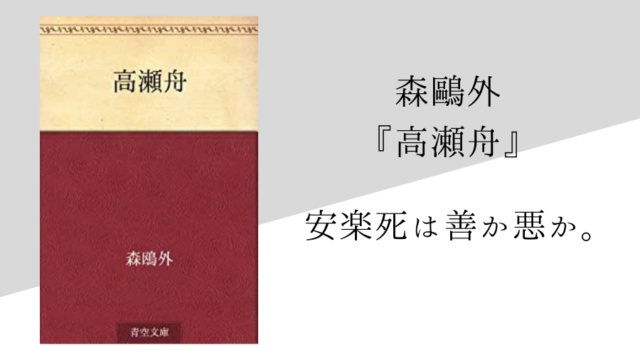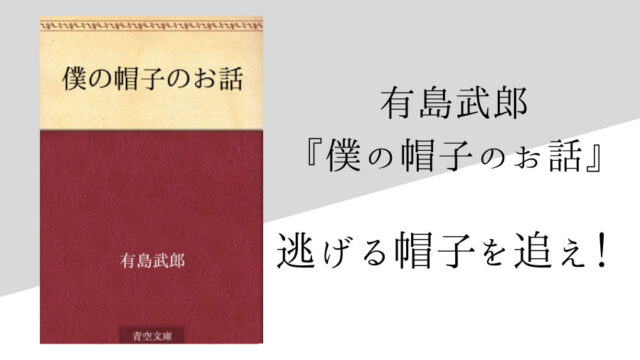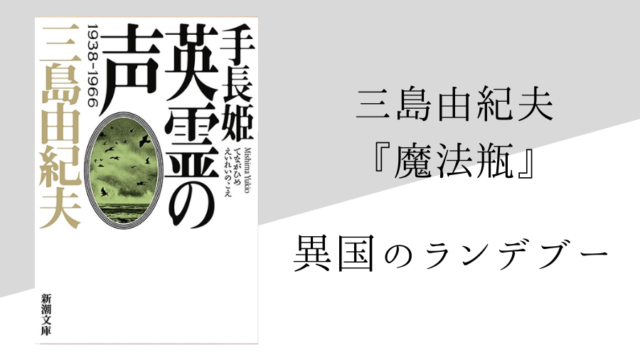「理想的な女子」の型を破った少女の行動にフォーカスした『快走』。
今回は、岡本かの子『快走』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!
『快走』の作品概要
| 著者 | 岡本かの子(おかもと かのこ) |
|---|---|
| 発表年 | 1938年 |
| 発表形態 | 雑誌掲載 |
| ジャンル | 短編小説 |
| テーマ | 抑圧と自由 |
『快走』は、1938年に文芸雑誌『令女界』(12月号)で発表された岡本かの子の短編小説です。窮屈な日常からの解放を求めて、1人の少女が大胆な行動に出る様子が描かれています。
『快走』は、2014年のセンター入試に採用された小説です。Kindle版は無料¥0で読むことができます。
『快走』のあらすじ
家で家事ばかりしていた道子は、窮屈な毎日にうんざりし気分転換に多摩川の土手に向かいます。学生時代ランニングをしていた道子は土手を走り、毎晩走りに行くようになります。
しかし人に見られては差しさわりがあるため、家族には銭湯に行くと言って外に出るのでした。そんな道子の行動を不審に思った母親はさまざまな策を講じます。
それでも道子はひそかにランニングを続けていましたが、ある日ついに両親にバレてしまうのでした…
登場人物紹介
道子(みちこ)
女学校在学中ランニングの選手をしていた少女。家に押し込められて仕事をする窮屈さから抜け出すため、家族には銭湯に行くと言って夜のランニングを始める。
陸郎(りくろう)
道子の兄。道子と仲が良い。
母
道子の母。道子の不可解な行動にあれこれと気を揉む。
父
道子の父。道子に一定の理解を示す。
『快走』の内容
この先、岡本かの子『快走』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。
一言で言うと
抑圧と自由
秘密のランニング
女学校を卒業したばかりの道子は、家にこもって家事に勤しむ毎日を送っています。ある日の夕方、気分転換に多摩川の土手に出た道子は、周囲に人がいないことを確認して土手をかけました。女学生時代ランニングの選手だった道子は、その快感を思い出します。
それからというもの、道子は家族に悟られないよう着物の下にランニングシャツと短パンを履き、銭湯に行くと言って家を出るようになりました。
両親の反応
しかし道子の母は、毎晩銭湯からの帰りが遅い道子を気にするようになります。母親は道子の兄の陸郎に跡をつけさせたり、昼間に道子と銭湯に行ったりして道子の動線を探りました。
しかし道子のランニングは、道子が走る姿を見ていた女学生時代の友人からの手紙で、両親にバレてしまいます。
母は「まあ、あの娘が、何ていう乱暴なことをしてるんでしょう。呼び寄せて叱ってやりましょうか」と言いますが、父は道子に一定の理解を示しました。
そして父の「自分の娘が月光の中で走るところを見たくなったよ」という言葉をきっかけに、2人は次の日の夜に道子のランニングをこっそり見に行くことにしました。
共感
道子は土手に着くとさっそく駆けだします。息を切らして土手にやって来た両親は、白いシャツを光らせて弾丸のように走る道子を認めました。母は、「あなたったら、まるで青年のように走るんですもの、追いつけやしませんわ」と父を追いかけます。
ひさびさに走る快感を覚えた両親は、道子のことを忘れて笑い合いました。
『快走』の解説
走りへの執着
道子と兄の会話や「縮こまった」「屈托」などという描写から、彼らが戦時中の抑圧された世を生きていることが推察できます。
また道子の場合、女性という立場のため出過ぎたことは控えなければならないという当時の共通認識によって余計に抑え込まれた状況であったことが分かります。
道子が初めて堤防を走ろうとするとき、「誰も見る人がない」と人目を気にしていることや、道子のランニングを知った母の「まあ、あの娘が、何ていう乱暴なことをしてるんでしょう」という発言から、当時は女性が着物の裾を端折ってパンツ姿で駆けることは野蛮なことみなされていたと推測できます。
道子は、走ることでこうした窮屈さから一時的に脱する快感を覚えてくり返し走りに行くようになります。若い肉体に閉じ込められた有り余るエネルギーが、出口を求めて噴き出す肉体的な悦びが道子を虜にしています。
しかし、道子は単にガス抜きとしてのランニングに魅せられているわけではないと思われます。
次第に脚の疲れを覚えて速力を緩めたとき、道子は月の光りのためか一種悲壮な気分に衝たれた――自分はいま溌剌と生きてはいるが、違った世界に生きているという感じがした。人類とは離れた、淋しいがしかも厳粛な世界に生きているという感じだった。(中略)道子は着物を着て小走りに表通りのお湯屋へ来た。湯につかって汗を流すとき、初めてまたもとの人間界に立ち戻った気がした。道子は自分独特の生き方を発見した興奮にわくわくして肌を強くこすった。
上記の引用で、走り終えた道子は「溌剌と生きている」感覚を味わうと同時に、人間の世界とは違うところに生きている感じを味わっています。なぜかというと、家を抜け出して人知れず普段は咎められるような大胆な行いをしているからです。
また、道子は人の目がないことを確認してから走っているのため、道子は自分と多摩川の堤防しかない空間に存在しています。
つまり、「人類とは離れた、淋しいがしかも厳粛な世界」というのは、一言で言うと「非日常」でしょう。道子にとってランニングとは、エネルギーを放出させる肉体的な快感と、窮屈な日常から逃避する精神的な充足の両方をもたらすものと考えられます。
『快走』の感想
主人公が不在のラスト
『快走』は、道子が川上へ走り去り、焦点が両親に移ったところで物語が締められます。
二人は月光の下を寒風を切って走ったことが近来にない喜びだった。二人は娘のことも忘れて、声を立てて笑い合った。
道子がフレームアウトした事実に加えて、上記引用部ではわざわざ「二人は娘のことも忘れて」という文が挿入されており、道子が不在であることが強調されています。つまり、このラストのシーンで光子がいないということは重要なポイントであると思われます。
主人公・道子の不在は何を表すのか。私は、両親が土手にやって来るシーンに注目しました。
「あれだ、あれだ」
父親は指さしながら後を振り返って、ずっと後れて駈けて来る妻をもどかしがった。妻は、はあはあ言いながら
「あなたったら、まるで青年のように走るんですもの、追いつけやしませんわ」
妻のこの言葉に夫は得意になり
「それにしてもお前の遅いことったら」
妻は息をついで
「これでも一生懸命だもんで、家からここまで一度も休まずに駈けて来たんですからね」
「俺達は案外まだ若いんだね」
「おほほほほほほほほほほ」
「あはははははははははは」
それまでは、両親は本心で話しているというよりかは、「父親とはこういうときこんな対応をすべき」「母親は夫にはこう、娘にはこう接するべき」というような型にはまった話し方をしている印象でした。
しかし道子を追って土手までやって来た両親は、家での堅苦しい形式ばった会話が一転、リズムよく軽快な会話をしています。
そして道子の不在と、両親の会話の「青年のよう」「若い」というキーワードには関係があると思うのです。
『快走』が執筆された当時、今以上にこうした性別役割分業の考えが根強かったと推測できます。「父親は威厳を保つべき」「母親は厳しくも優しく子を想うべき」という押し付けられた役割に、両親は知らぬ間に疲れていたと考えられないでしょうか。
両親は思いっきり走ることで道子のように開放的な気持ちになり、2人の間にあった深刻・真剣・厳格な雰囲気がふっと和らぎます。
同時に両親が道子の存在を忘れるという描写は、自身が親であることを忘れる=両親が親という役割を一時的に捨てて解放されることを示しているのではないでしょうか。「青年のよう」「若い」という単語は、それを示唆するために配置されていると考えます。
最後に
今回は、岡本かの子『快走』のあらすじと内容解説・感想をご紹介しました。
ぜひ読んでみて下さい!
↑Kindle版は無料¥0で読むことができます。